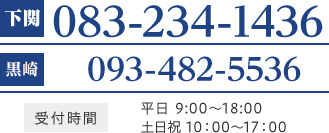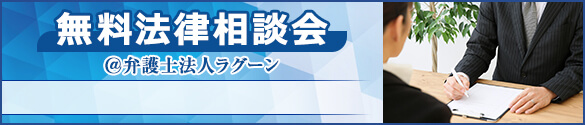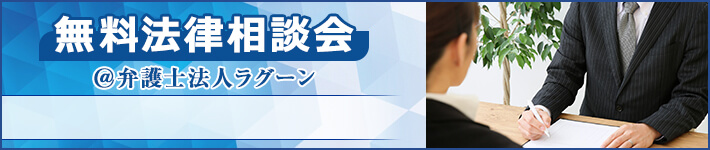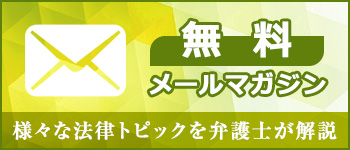第118回 中途採用者に対する採用拒否
弁護士の内田です。
最近、タブレットで絵を描いています。
弁護士業界は、文字、文字、文字、ばかりで近寄りがたいので、グラフィックな面での工夫も必要かなと思った次第です。
実際に描いてみるとこれが中々難しいもので、小学生が描いた感が抜けません。色々と本を読んでみると、理論や技法がたくさんあって、センスだけの世界ではないことを知りました。センスがなくてもある程度は上手くなれるということでもありますから、今しばらく頑張ってみようと思います。
さて、本日のテーマは、「中途採用者に対する採用拒否」です。
近時、履歴書に虚偽の情報を記載していた中途採用者に対する採用拒否を無効とする判決が出されましたので(東京高裁令和6年12月17日判決)、今回はそれを解説します(以下、「本裁判例」と言います。)。
最近は中途採用も盛んになっていますので、しっかりと押さえておきましょう。
まず、いわゆる「内定」については有名な判例があり、内定とは、始期付き留保解約権付雇用契約だと解されています。要するに、働く日が先に決まっていて、でも解約(内定取消)権が留保されている雇用契約です。
そして、この留保解約権ですが、無条件に行使できるわけではなく、会社が内定通知した当時に知らなかった事実で、これを理由に内定取消することが、解約権を留保している趣旨や目的に照らして、客観的に合理的と認められて社会通念上相当と認められる場合でなければ行使できません。
これが結構、会社側には厳しく認定されていて、多少、履歴書等に虚偽の事実が記載されていても「就業に支障はないから別にいいでしょ。」という具合で会社側が負けることが多いです。
まず、本裁判例は示した重要な点は、上記の判例は中途採用者にも当てはまるということです。新卒採用者限定の判例ではないということです。
本裁判例は、「単に履歴書等の書類に虚偽の事実を記載し或いは真実を秘匿した事実が判明したのみならず、その結果、労働力(労働者)の資質、能力を客観的合理的に見て誤認し、企業の秩序維持に支障をきたすおそれがあるものとされたとき、又は、企業の運営に当たり円滑な人間関係、相互信頼関係を維持できる性格を欠いていて企業内にとどめおくことができないほどの不正義性が認められる場合に限り、上記解約権の行使として有効なものと解すべき」としています。
かなり会社側に厳しい内容になっています。個人的には、嘘をついて入社してこようとしていると分かった時点で「円滑な人間関係」「相互信頼関係」を築くのは難しいのではないかと思いますが、裁判所はもう少し突っ込んで嘘の内容を吟味します。
本裁判例は、結果として、労働者が経歴詐称の程度が履歴書に記載された期間の半分近くを占めるものであることなどを認定して、留保解約権行使を有効と判断しています。
どのくらいの虚偽記載や資質不足があれば本採用を拒否できるのか、はっきりしないところは未だにありますが、今後の裁判例の蓄積によってその範囲は明らかになってゆくことでしょう。
虚偽記載=内定取消できるわけではありませんので、虚偽記載の事実が判明してもすぐに内定取消せず、まずは弁護士に相談しましょう。
いかがだったでしょうか。
本裁判例もそうですが、最近、裁判所が労働者に厳しめになっていると言われているようです。いわゆる買い手市場のとき、職を失うことが労働者にとって大きな不利益であったことから、裁判所は雇用を終わらせること(解雇や留保解約権行使)に極めて消極的であったようです。
しかし、今は売り手市場で、わりと転職もしやくなっていますので、ひょっとしたら裁判所もその辺りの統計などを確認して事実認定を緩やかに変えていっているのかもしれません。